
世界の貧しさと闘う6 共に暮らし指導者育成
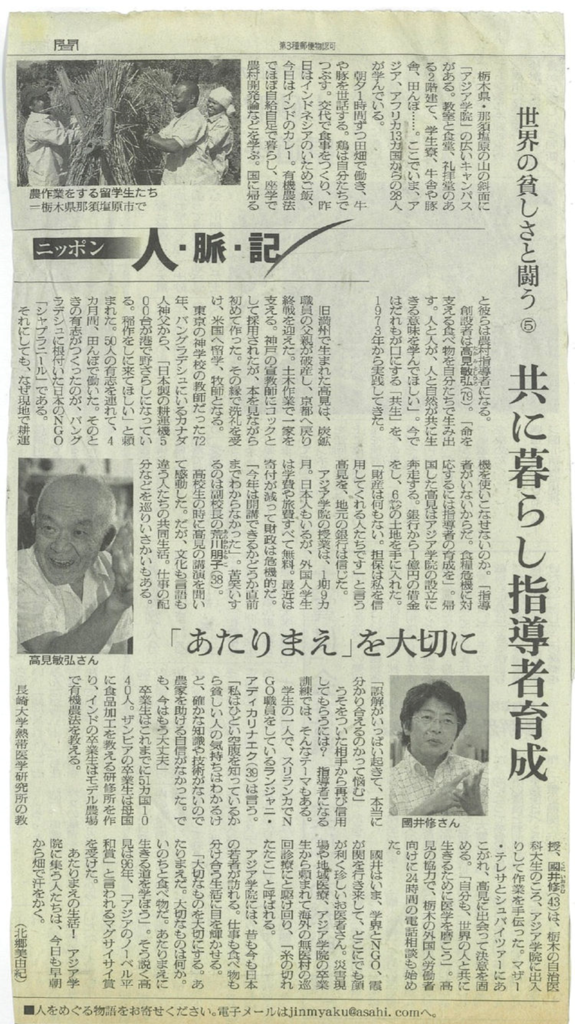
世界の貧しさと闘う6 共に暮らし指導者育成
栃木県・那須塩原の山の斜面に「アジア学院」の広いキャンパスがある。教室と食堂、礼拝堂のある2階建て、学生寮、牛舎や豚舎、田んぼ…。ここでいま、アジア、アフリカ13カ国からの28人が学んでいる。
朝夕1時間ずつ田畑で働き、牛や豚を世話する。鶏は自分たちでつぶす。交代で食事をつくり、昨日はインドネシアのいためご飯、今日はインドのカレー。有機農法でほぼ自給自足で暮らし、座学で農村開発論などを学ぶ。国に帰ると彼らは農村指導者になる。
創設者は高見敏弘(79)。「命を支える食べ物を自分たちで生み出す。人と人が、人と自然が共に生きる意味を学んでほしい」。今ではだれもが口にする「共生」を、1973年から実践してきた。
旧満州で生まれた高見は、炭鉱職員の父親が破産し、京都へ戻り終戦を迎えた。土木作業で一家を支える。神戸の宣教師にコックとして採用されたが、本を見ながら初めて作った。その縁で洗礼を受け、米国へ留学、牧師となる。
東京の神学校の教師だった72年、バングラデシュにいるカナダ人神父から、「日本製の耕運機500台が港で野ざらしになっている。稲作をしに来てほしい」と頼まれた。50人の有志を連れて、4カ月間、田んぼで働いた。そのときの有志がつくったのが、バングラデシュに根付いた日本のNGO「シャプラニール」である。それにしても、なぜ現地で耕運機を使いこなせないのか。「指導者がいないからだ。食糧危機に対応するには指導者の育成を」。帰国した高見はアジア学院の設立に奔走する。銀行から1億円の借金をし、6ヘクタールの土地を手に入れた。「財産は何もない。担保は私を信用してくれる人たちです」と言う高見を、地元の銀行は信じた。
アジア学院の授業は、1期9カ月。日本人もいるが、外国人学生は学費や旅費すべて無料。最近は寄付が減って財政は危機的だ。「今年は開講できるかどうか直前までわからなかった」。苦笑いするのは副校長の荒川朋子(38)。
高校生の時に高見の講演を聞いて感動した。だが、文化も言語も違う人たちの共同生活。仕事の配分などを巡りいさかいもある。
「誤解がいっぱい起きて、本当に分かり合えるのかって悩む」
うそをついた相手から再び信用してもらうには? 指導者になる訓練では、そんなテーマもある。
学生の一人で、スリランカでNGO職員をしているランジャニ・アディカリナエク(39)は言う。「私はひどい空腹を知っているから貧しい人の気持ちはわかるけど、確かな知識や技術がないので農家を助ける自信がなかった。でも、今はもう大丈夫」
卒業生はこれまでに51カ国1040人。ザンビアの卒業生は母国に食品加工を教える研修所を作り、インドの卒業生はモデル農場で有機農法を教える。
長崎大学熱帯医学研究所の教授、國井修(43)は、栃木の自治医科大生のころ、アジア学院に出入りして作業を手伝った。マザー・テレサとシュバイツァーにあこがれ、高見に出会って決意を固める。「自分も、世界の人と共に生きるために医学を磨こう」。高見の協力で、栃木の外国人労働者向けに24時間の電話相談も始めた。
國井はいま、学界とNGO、霞が関を行き来して、どこにでも顔が利く珍しいお医者さん。災害現場や地域医療、アジア学院の卒業生から頼まれて海外の無医村の巡回診療にと駆け回り、「糸の切れたたこ」と呼ばれる。
アジア学院には、昔も今も日本の若者が訪れる。仕事も食べ物も分け合う生活に目を輝かせる。
「大切なものを大切にする。あたりまえだ。大切なものは何か。いのちと食べ物だ。あたりまえに生きる道を学ぼう」。そう説く高見は96年、「アジアのノーベル平和賞」と言われるマグサイサイ賞を受けた。
あたりまえの生活! アジア学院に集う人たちは、今日も早朝から畑で汗をかく。
(北郷美由紀)
※本記事の出典や掲載日時は不明です。


